社会人としてのキャリアがスタートする20代は、自由な時間とお金を手に入れ、人生が大きく動き出す時期です。しかし同時に、将来のために「貯金」を意識し始める人も多いのではないでしょうか。周りの同世代がどれくらい貯金しているのか、自分はいくら貯金すれば安心できるのか、具体的なイメージが湧かずに漠然とした不安を感じている人も少なくないでしょう。お金の悩みは、なかなか他人には相談しにくいものです。この記事では、20代の貯金の平均額といったリアルな情報から、将来のライフプランを見据えた賢い目標設定のコツ、そして今日から始められる具体的な貯金方法や資産形成の考え方まで、あなたの「お金の不安」を「安心」に変えるためのヒントを分かりやすく解説していきます。
20代のリアルな貯金事情、平均はいくら?
まずは、気になる同世代のお財布事情から見ていきましょう。他の人がどれくらい貯金しているかを知ることは、自分の現在地を客観的に把握し、今後の目標を設定する上での大切な参考になります。ただし、ここで紹介する平均額はあくまで一つの目安です。大切なのは、他人と比べて一喜一憂するのではなく、自分自身の価値観やライフプランに合わせた計画を着実に立てていくことにあります。
平均貯金額に隠された実態
金融広報中央委員会が毎年実施している「家計の金融行動に関する世論調査」という信頼性の高いデータを見てみると、20代単身世帯の金融資産保有額、つまり預貯金や保険、有価証券などを合わせた額の平均値は、百数十万円となっています。この数字だけを見ると、「みんな意外と貯めているんだな」と焦りを感じるかもしれません。しかし、この「平均値」という数字には注意が必要です。一部の非常に多くの貯金を持つ人が全体の数値を大きく引き上げているため、実感とは少し離れている可能性があります。そこで、より実態に近いとされるのが「中央値」です。これは、データを小さい順に並べたときにちょうど真ん中に来る値のことで、同調査では数十万円という結果になっています。このことから、多くの20代はまだ数百万円といった大きな貯蓄を築けているわけではなく、コツコツと貯め始めている段階であることがうかがえます。
貯金ゼロの現実と収入との向き合い方
一方で、同じ調査では金融資産を全く保有していない、いわゆる「貯金ゼロ」の世帯も一定数存在することも示されています。社会人になりたての頃は、新しい生活を始めるための出費がかさみ、給料のほとんどが生活費に消えていくという状況も珍しくありません。また、月々の手取り収入から家賃や光熱費、通信費といった固定費や、人によっては奨学金返済などを差し引くと、自由に使えるお金はごくわずかという人も多いでしょう。収入の額によって貯金に回せる金額が大きく変わるのは当然のことです。大切なのは、収入が低いからと諦めてしまうのではなく、今の自分の収入の中で、たとえ少額でも確実に貯金の習慣を身につけるという前向きな視点を持つことです。月々数千円からでも、始めることに大きな意味があります。
なぜ貯金が必要?20代が考えるべき未来のライフプラン
「なんとなく将来が不安だから」という漠然とした理由で貯金を始める人も多いかもしれません。しかし、その目的が明確であればあるほど、日々の節約や貯金に対するモチベーションを高く維持しやすくなります。20代のうちに、これから先の人生で起こりうる様々な出来事、すなわちライフプランと、それに伴って必要となるお金について具体的にイメージを膨らませてみましょう。そうすることで、貯金が単なる「我慢」ではなく、未来の自分の夢や安心を形作るための、ポジティブな「自己投資」であると捉えられるようになるはずです。
近い将来に訪れるライフイベントへの備え
20代から30代にかけては、結婚や出産、マイホームの購入といった、人生における大きなライフイベントが次々と訪れる可能性が高い時期です。例えば、結婚を考えた場合、結婚式の費用や新婚旅行、新生活を始めるための家具や家電の購入などで、数百万円単位のまとまったお金が必要になることが一般的です。また、いつか自分の家を持ちたいと考えるなら、住宅ローンの頭金として物件価格の1割から2割程度を用意することが理想とされています。これらの大きな出費は、突然用意できるものではありません。将来、お金が理由で自分の望む選択を諦めることがないよう、早い段階から計画的に準備を進めておくことが、夢の実現への近道となります。
遠い未来への備えとなる老後資金の考え方
「老後なんて、まだまだ先の話で実感が湧かない」と感じるのが20代の正直な気持ちかもしれません。しかし、実はこの時期から老後資金の準備を始めることには、計り知れないほどの大きなメリットが存在します。その最大の理由は、「時間」を味方につけられるからです。時間をかければ、後ほど説明する「複利」の効果によって、たとえ毎月の積立額が少額であっても、雪だるま式に資産を大きく育てていくことが可能になります。人生100年時代と言われる現代において、公的な年金制度だけでゆとりある老後の生活を送ることは、残念ながら難しくなっていくと予想されています。若いうちから長期的な視点で資産形成への意識を向けておくことが、将来の経済的な自由と安心を手に入れるための最も確実な方法の一つと言えるでしょう。
貯金目標の設定、手取りからの具体的なステップ
貯金の必要性を自分事として理解できたら、次はいよいよ具体的な目標設定のフェーズです。ただ闇雲に節約を始めるのではなく、無理なく、そして着実に貯金を増やしていくためには、まず自分自身の収入と支出を正確に把握することが不可欠な第一歩となります。現実的で達成可能な目標を立て、それをクリアするための具体的な計画に落とし込んでいきましょう。ここでは、毎月の手取り収入を基準とした目標額の考え方と、その土台となる日々の支出管理を成功させるコツについて詳しく解説します。
手取り収入から導き出す現実的な貯金割合
一般的に、無理なく続けられる貯金の目安は、手取り収入の10%から20%程度と言われています。例えば、手取りが20万円であれば、月々2万円から4万円を貯金に回すというのが一つの基準になります。しかし、これはあくまで一般的な目安であり、全ての人に当てはまるわけではありません。実家で暮らしているか、都市部で一人暮らしか、あるいは月々の奨学金返済があるかなど、個々人が置かれている状況によって、家計の構造は大きく異なります。大切なのは、まず自分の手取り額を正確に把握し、そこから家賃などの固定費を差し引いた上で、無理のない範囲で「これなら毎月続けられそう」と思える金額を見つけることです。そして、給料が振り込まれたら、使う前にその金額を別の口座に移してしまう「先取り貯金」を実践するのが成功の鍵です。
支出の「見える化」が成功の鍵、家計簿の重要性
意欲的に貯金目標を立てたとしても、日々の支出をしっかりと管理できていなければ、計画はあっという間に崩れてしまいます。そこで、ぜひ習慣にしていただきたいのが、家計簿をつけることです。かつてはノートに手書きするのが主流でしたが、最近ではスマートフォンにインストールするだけで使える、高機能な家計簿アプリがたくさん登場しています。レシートをスマートフォンのカメラで撮影するだけで品目や金額を自動で読み取ってくれたり、クレジットカードや銀行口座と連携して利用履歴を自動で取り込んでくれたりするアプリも多く、手間をかけずに支出を「見える化」できます。まずは1ヶ月でも良いので記録を続けてみましょう。自分が何にどれくらいのお金を使っているのかを客観的に把握することで、知らず知らずのうちに使っていた無駄な出費を発見しやすくなり、効果的な支出管理へと繋がっていきます。
貯金を加速させる、20代からの資産形成入門
毎月の貯金が習慣になり、少しずつお金が貯まっていくのを実感できるようになったら、ぜひ次の一歩として「お金にも働いてもらう」という発想、すなわち資産形成を始めてみることを検討しましょう。歴史的な低金利が続く現代の日本では、お金を銀行の普通預金に預けておくだけでは、利息はほとんど付かず、資産が大きく増えることは期待できません。もちろん投資にはリスクが伴いますが、そのリスクを正しく理解し、コントロールしながら少額から始めることで、貯金だけの場合よりも効率的に資産を増やせる可能性があります。ここでは、20代が知っておくべき資産形成の基礎知識と、国も推奨している初心者におすすめの制度についてご紹介します。
投資への第一歩として最適なNISAの活用法
「投資」と聞くと、専門的な知識が必要で、多額の資金がないと始められない難しいもの、というイメージを抱いている方も多いかもしれません。しかし、それは過去の話です。特に20代の投資デビューに最適な制度として、国が用意してくれているのが「NISA(ニーサ)」です。これは少額投資非課税制度の愛称で、通常であれば投資で得られた利益(配当金、分配金、譲渡益)に対してかかる約20%もの税金が、NISA口座内での取引に限って非課税になるという、非常にお得な制度です。2024年からは新しいNISA制度がスタートし、非課税で投資できる上限額が大幅に拡大され、制度自体も恒久化されるなど、より使いやすく、長期的な資産形成に取り組みやすい仕組みへと生まれ変わりました。まずはこのNISAの仕組みをしっかりと理解し、月々数千円といった無理のない金額から始めてみることが、資産形成への大きな一歩となります。
資産形成を成功に導く3つの基本原則
投資の世界で、リスクを抑えながら安定した成果を目指すための重要な考え方として、古くから伝えられているのが「長期・積立・分散」という3つの基本原則です。これは、投資の専門家でなくても実践できる、非常に強力な手法です。「長期」とは、日々の価格の上下に一喜一憂することなく、長い時間をかけて経済の成長と共に資産が育つのをじっくりと待つ姿勢のこと。「積立」とは、毎月1万円ずつ、というように決まった金額を定期的に買い続けることで、価格が高いときには少なく、安いときには多く買うことになり、結果的に平均購入単価を抑える効果(ドルコスト平均法)が期待できる手法です。「分散」とは、「卵は一つのカゴに盛るな」という格言に例えられるように、投資先を特定の国や資産に集中させるのではなく、複数の対象に分けて投資することで、予期せぬ値下がりが起きた際の影響を和らげる考え方です。この3つの原則を意識するだけで、投資における失敗の確率を大きく下げることができます。
金融リテラシーを高めて、賢くお金と付き合うために
ここまで、貯金の具体的な目標設定の方法や、NISAを活用した資産形成の入門知識について解説してきました。しかし、これらのテクニックを実践し、変化の激しい時代を乗りこなし、より豊かな人生を送るためには、その土台となる「金融リテラシー」、すなわちお金に関する正しい知識や情報を取捨選択し、適切に判断する能力を高めていくことが不可欠です。お金の知識は、あなたを悪質な金融商品や詐欺などのトラブルから守ってくれる盾となり、同時に、人生の様々な局面でより良い選択をするための羅針盤となります。日々の生活の中で少しずつでも学びを深め、自分自身のお金の教養を育てていきましょう。
20代の課題、奨学金返済との上手な付き合い方
現代の多くの20代にとって、奨学金の返済は家計における無視できない負担の一つとなっています。毎月の返済額が、貯金や自己投資に回すお金を圧迫していると感じる人も少なくないでしょう。しかし、奨学金は、あなたが学ぶ機会を得るために行った、未来の自分への価値ある投資であったことも事実です。まずは、ご自身の返済総額や月々の返済額、返済期間といった契約内容を改めて正確に把握し、毎月の支出として確実に予算に組み込むことが重要です。資金に余裕ができた場合に繰り上げ返済を検討する際には、それによって得られる利息の軽減効果と、手元の現金が減ってしまうリスクを天秤にかける必要があります。貯金や資産形成とバランスを取りながら、計画的に返済を進めていく賢明な判断が求められます。
変化し続けるライフステージとお金の関係
私たちの人生には、就職、転職、結婚、出産・子育て、住宅購入、そしてリタイアなど、様々なライフステージが待ち受けています。そして、それぞれのステージで必要となるお金の種類や額は大きく異なり、お金との付き合い方も常に変化していきます。例えば、独身時代は自己投資にお金を使うことができても、家庭を持てば教育費や住宅費が優先されるようになるかもしれません。20代のうちから金融リテラシーの基礎をしっかりと身につけておくことで、こうしたライフステージの変化にも慌てることなく、柔軟に対応できるようになります。将来の選択肢を狭めてしまわないためにも、公的機関のウェブサイトや信頼できる書籍などを通じて継続的にお金の知識を学び、自分自身の価値観に合ったお金の使い方、そして増やし方を見つけていくことが、これからの人生を豊かにする上で極めて大切です。
まとめ
20代の貯金は、漠然とした不安を解消するためだけのものではなく、これからの長い人生を自分らしく、豊かに歩んでいくための大切な土台作りです。周りの人がいくら貯めているかという平均額に一喜一憂するのではなく、まずはご自身の「手取り」収入と日々の「支出」を正確に把握することから全てが始まります。そして、結婚や住宅購入といった近い将来の夢から、まだ遠い未来に思える老後資金への備えまで、具体的な目的を持つことが、貯金を継続させる何よりのエネルギー源となります。家計簿アプリなどを賢く活用して支出管理を習慣化し、無理のない範囲で現実的な目標額を設定することが成功の秘訣です。さらに、日々の貯金に加えて、NISAなどを利用した「長期・積立・分散」投資を少額からでも始めることで、お金にも働いてもらうという視点が身につき、資産形成をより効率的に進めることができるでしょう。奨学金返済といった20代特有の課題とも上手に向き合いながら、金融リテラシーという一生モノのスキルを磨いていくことこそが、変化の多い時代を賢く、そして力強く生き抜くための確かな力となります。今日からできるその小さな一歩が、10年後、20年後のあなたの「安心」と「自由」に、そして輝く未来に間違いなくつながっています。
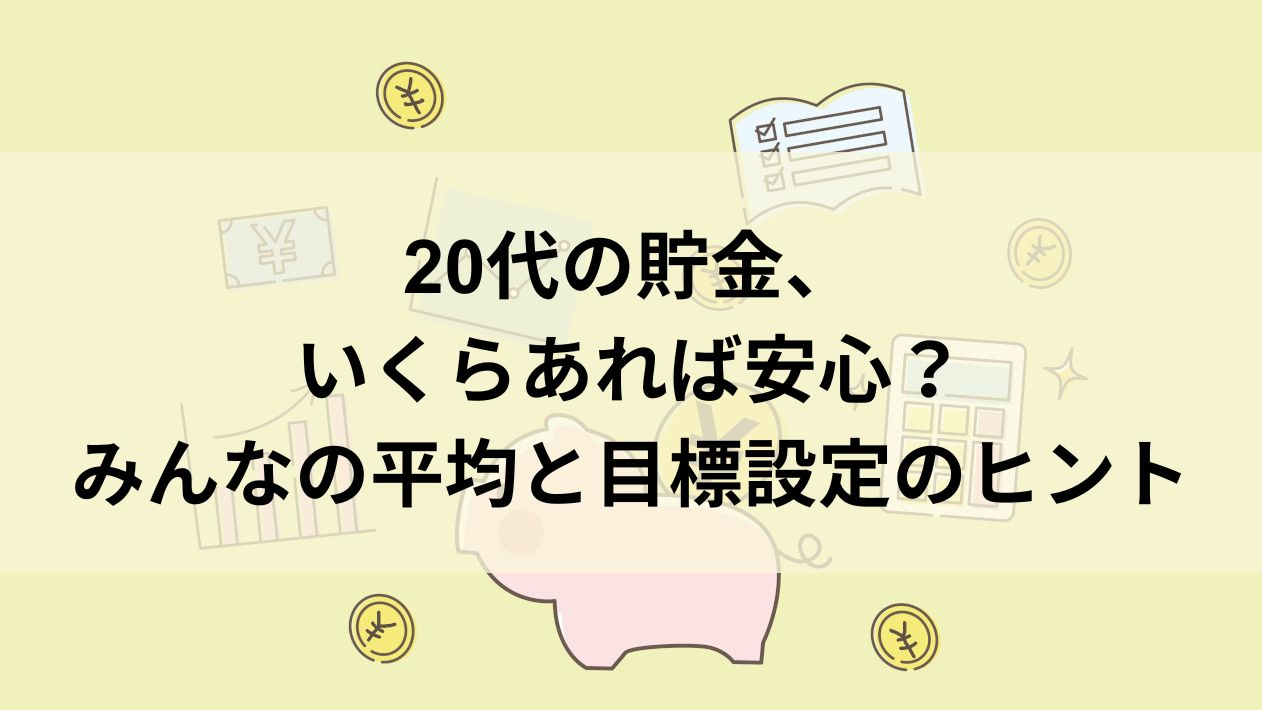
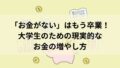
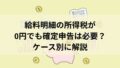
コメント